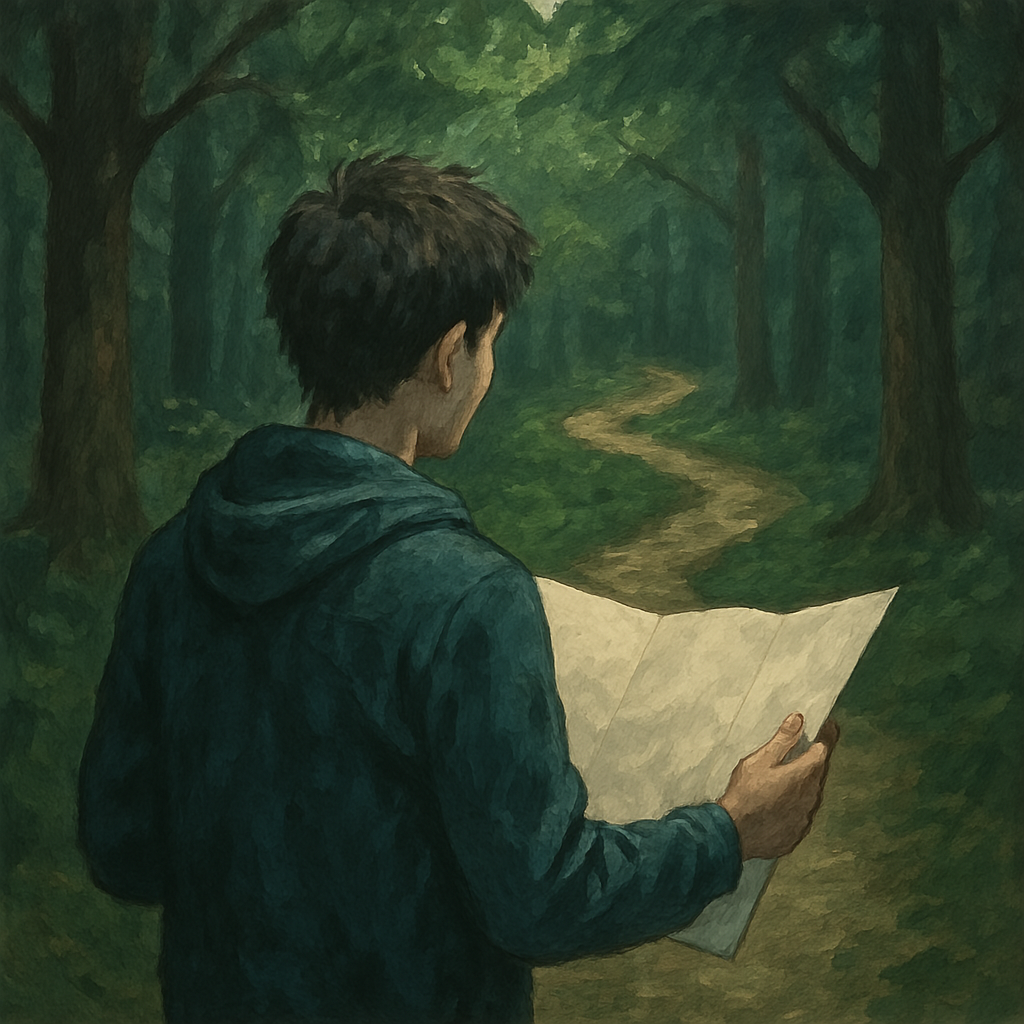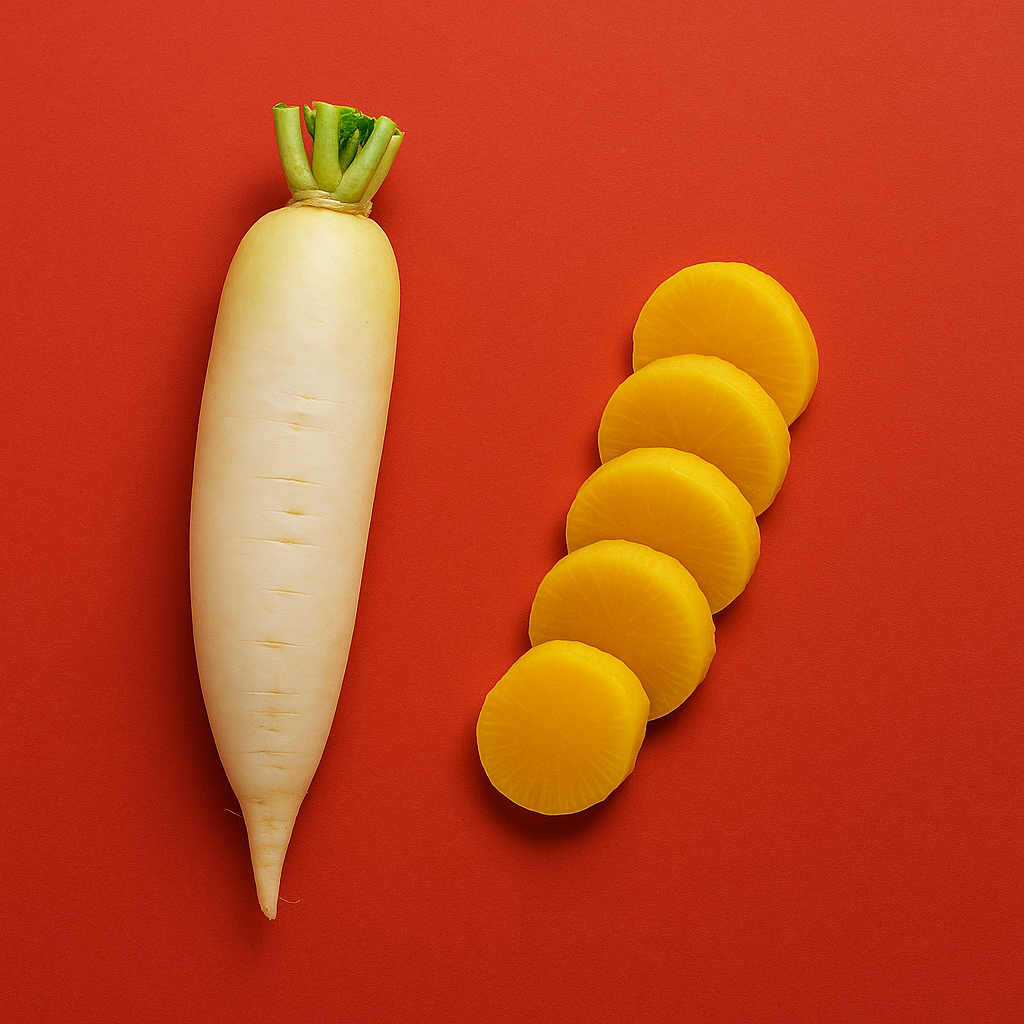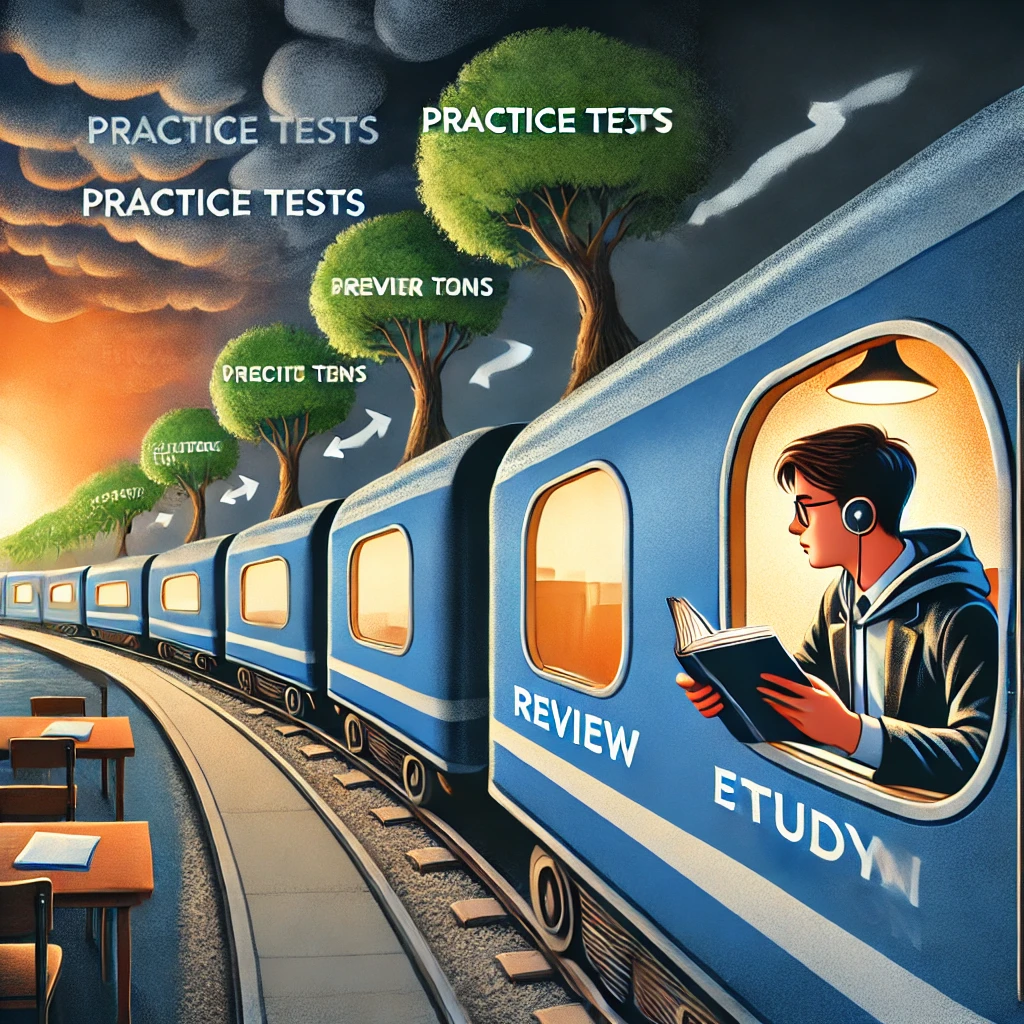口と雰囲気に漂う今後の道のり

言葉遣いの悪さがもたらすデメリット 〜買い物と受験勉強の共通点〜
コンビニやスーパーで買い物をする際、店員の言葉遣いが悪かったらどう感じるでしょうか?
「いらっしゃいませ」もなく、商品を雑に扱い、レジで「◯◯円っす」と投げやりに言われたら、不快な気持ちになりますよね。
実は、これは受験勉強にも通じる話です。言葉遣いの悪さは、相手との信頼関係を壊すだけでなく、自分自身の思考力や成績にも悪影響を及ぼすのです。
この記事では、
1. 買い物における悪い言葉遣いのデメリット
2. 受験生がネガティブな言葉遣いをするデメリット
この二つを比較しながら解説していきます。
① 言葉遣いの悪いスタッフから商品を買うデメリット
あなたがコンビニで飲み物を買おうとしたとき、店員の対応が次のどちらだったら気持ちよく買い物できるでしょうか?
| 店員A(丁寧な対応) | 店員B(悪い対応) |
| 「いらっしゃいませ!」「◯◯円になります」「ありがとうございました!」 | 「あー、◯◯円っす」「……(無言で袋を投げる)」「(ため息をつく)」 |
店員Bの対応を受けたら、もう二度とその店には行きたくないと感じるでしょう。言葉遣いの悪いスタッフがいるお店は、客の満足度が下がり、最終的には売上の低下につながります。
また、悪い言葉遣いは周囲の雰囲気を悪くし、他のスタッフや客にも伝染してしまう危険性があります。
② 受験生がネガティブな言葉遣いをするデメリット
次に、受験勉強における言葉遣いを考えてみましょう。
受験生が「もう無理」「どうせダメだ」「疲れた、やりたくない」といったネガティブな言葉を頻繁に使うと、どのような影響があるでしょうか?
| ポジティブな言葉を使う場合 | ネガティブな言葉を使う場合 |
| 「少しずつ進んでる!」「この問題、あとちょっとで解けそう」「工夫すれば何とかなるかも」 | 「もう無理、絶対できない」「どうせ俺はバカだから」「こんなのやっても意味ない」 |
ネガティブな言葉を使うと、自分自身の脳に「できない」という暗示をかけてしまい、本当に思考が停止してしまうのです。
さらに、周囲に対しても悪影響を与えます。友達やクラスメイトが前向きに勉強している中で、「どうせ無理だよ」と言われたら、やる気を削がれてしまいますよね。
③ 言葉遣いの違いが生み出す「信頼」と「成果」
| シチュエーション | 言葉遣いの良い場合 | 言葉遣いの悪い場合 |
| 買い物(接客) | 信頼が生まれ、リピーターが増える | 客が不快になり、店の評価が下がる |
| 受験勉強 | 自分の成績向上につながる仲間と励まし合える | 思考力が低下する周囲のモチベーションを下げる |
このように、言葉遣いは単なる「話し方」の問題ではなく、自分の未来に直結する重要な要素です。
④ どうすれば言葉遣いを改善できるのか?
では、受験生がネガティブな言葉遣いを改善するためにはどうすればいいのでしょうか?
次の3つの方法を試してみてください。
1. 「できる」「やってみる」を口癖にする
例:「この問題、できるかな?」→「工夫すればできるかも!」
2. ポジティブな表現に言い換える
例:「もうダメだ」→「まだ改善の余地がある」
3. 他人に悪影響を与えない言葉選びをする
例:「俺はダメだ」→「もうちょっと工夫してみよう」
言葉遣いは、習慣です。普段から意識していれば、自然とポジティブな言葉が増えていきます。
⑤ まとめ:言葉遣いの違いが生む「未来」
• 悪い言葉遣いは、買い物の場面でも受験勉強でもマイナスの影響を与える。
• ネガティブな言葉は、自分の思考力を下げ、周囲の人のモチベーションも奪う。
• ポジティブな言葉遣いを意識することで、信頼を得られ、結果もついてくる。
言葉には力があります。
「できる」「工夫すれば何とかなる」
そうした言葉を使い続けることで、受験勉強だけでなく、将来の人間関係や仕事にもプラスの影響を与えます。
コンビニの店員が心のこもった接客をするように、自分の言葉遣いも意識して、より良い未来をつかみましょう!