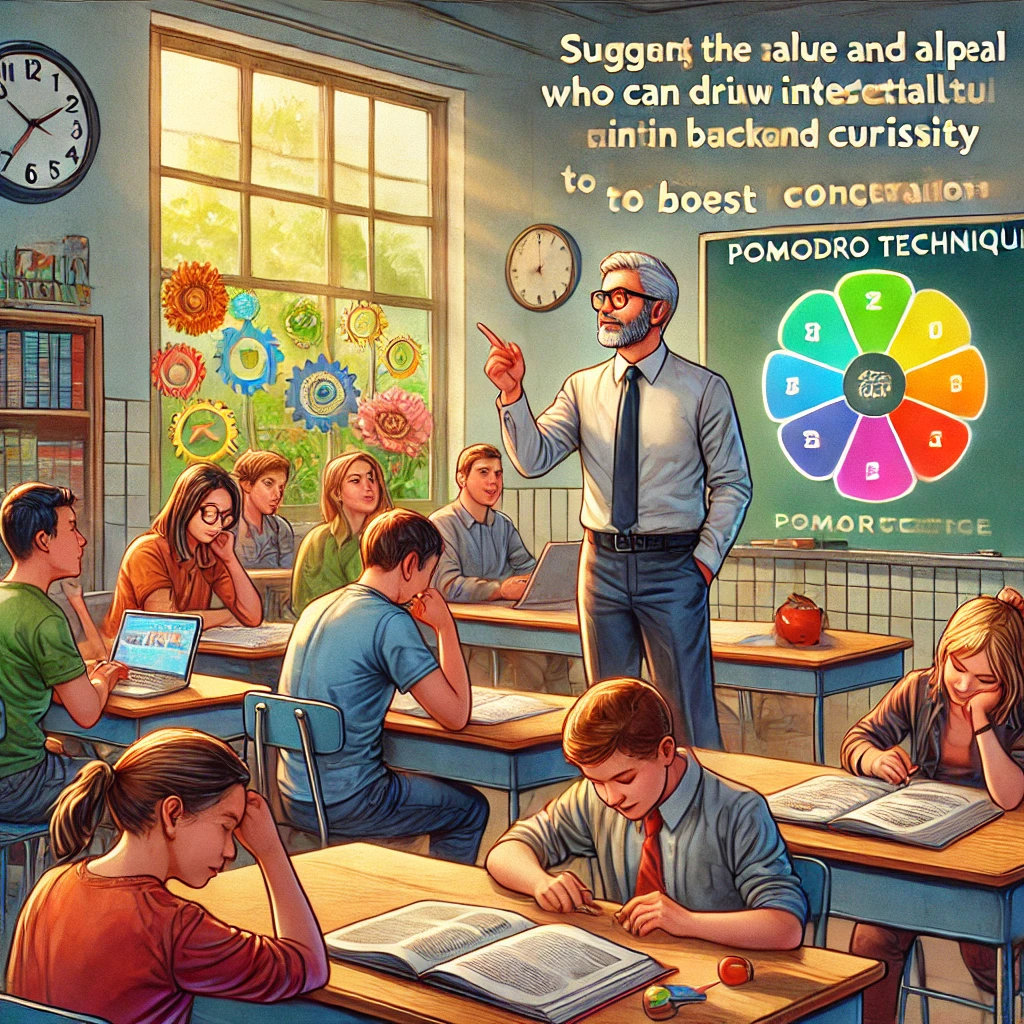積極的な注意をして静寂をキープする
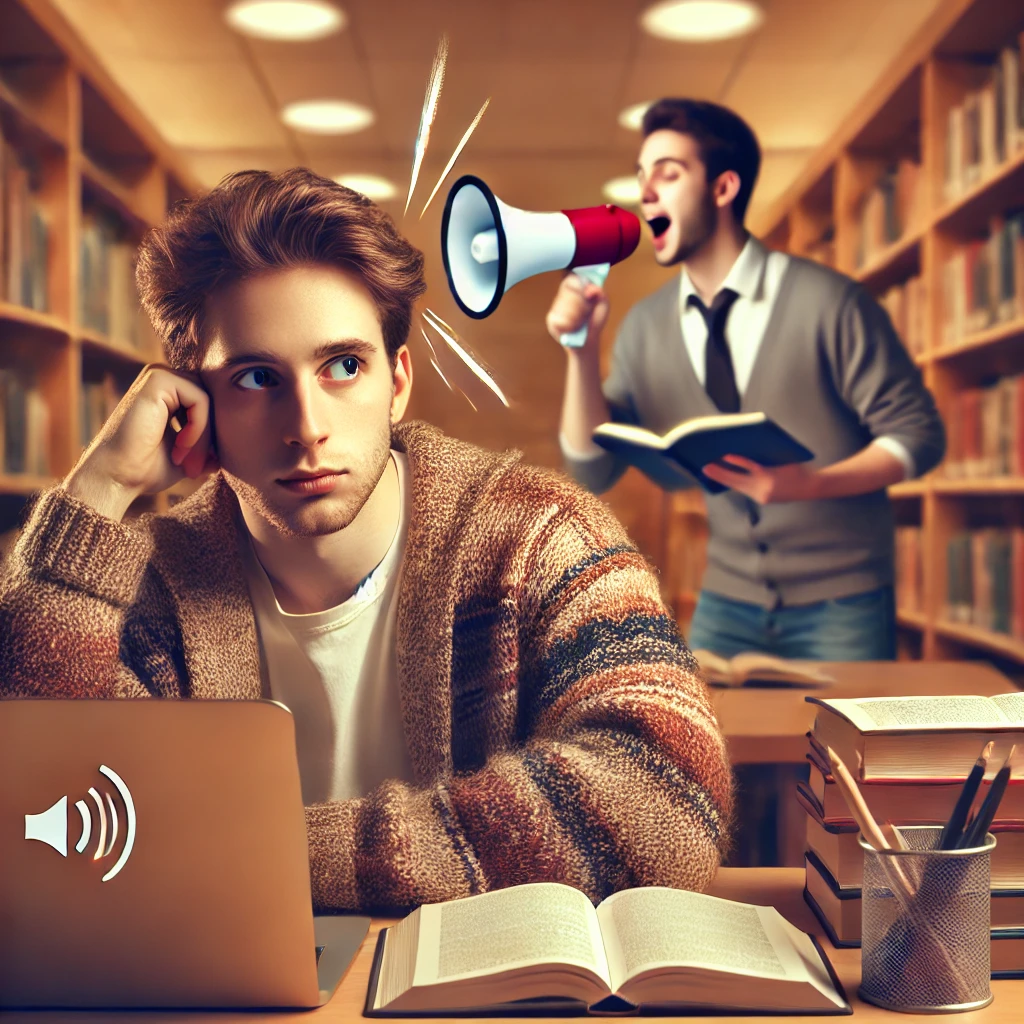
【受験生の不可抗力ストレス対策】隣の席のタイピング音が気になるときの対処法
受験生にとって集中力を維持することは非常に重要ですが、周囲の環境によって妨げられることがあります。その一例が「となりの席のタイピング音」です。本人に悪気がなくても、カタカタとした打鍵音が気になってしまうことはよくあります。
本記事では、こうした状況にどう対処すべきか、また受験生が避けられないストレスにどう向き合えばよいのかを解説します。
1. となりの席のタイピング音が気になるときの対応策
① まずは「本当に耐えられない音か」冷静に判断する
人間は一度気になり始めると、その刺激を増幅して感じてしまうことがあります。「本当に耐えられないレベルの音なのか?」と、自分の反応を客観的に見直してみましょう。
② 気にならないように工夫する
もし「そこまで大きな音ではないが、意識すると気になる」という場合は、以下の対策を試してみましょう。
• イヤホンや耳栓を活用する(ノイズキャンセリングイヤホンが特に効果的)
• ホワイトノイズを流す(環境音アプリなどを利用)
• 自分の注意を別のことに向ける(例えば、勉強に集中することで音を意識しなくする)
③ 可能なら座席を変更する
学校や塾など、席が自由に選べる場合は、席替えを考えてみましょう。特に図書館や自習室では、静かな場所を選ぶことが重要です。
④ 直接相手に伝える(慎重に!)
「相手が気づいていないだけで、配慮してもらえれば改善する」というケースもあります。ただし、伝え方を間違えると相手を不快にさせてしまうため、以下のように配慮しましょう。
OKな伝え方
✅ 「すみません、少し音が気になってしまって……もし可能なら少しだけ打鍵音を抑えていただけますか?」
NGな伝え方
❌ 「タイピング音がうるさいんですけど!」(攻撃的すぎる)
❌ 「もっと静かにしてもらえませんか?」(相手が悪いと決めつける言い方)
相手が善意で対応してくれた場合は、必ず「ありがとうございます!」と感謝を伝えましょう。
2. 受験生が避けられないストレスへの対処法
試験勉強を進める中で、周囲の環境や不可抗力によるストレスを完全になくすことはできません。以下の方法でストレスを減らし、集中力を維持しましょう。
① 「雑音耐性」をつけるトレーニング
実は、多少の雑音がある環境でも集中できるようになることは可能です。例えば、以下の方法を試してみましょう。
• カフェや駅などの少しうるさい場所で勉強する
• あえて小さなBGMを流しながら勉強する(無音環境よりも集中力が持続しやすい)
• タイピング音を自分で出してみる(「慣れる」ことで気にならなくなる場合も)
② 「環境が完璧でないこと」を受け入れる
試験本番も、周囲の環境が完璧に整っているとは限りません。例えば……
• 隣の受験生が貧乏ゆすりをしている
• 試験官の足音や物音が気になる
• 教室の外の工事音が聞こえる
こうした状況に対して「自分ではコントロールできないこと」と割り切ることで、ストレスを減らすことができます。
③ 「集中スイッチ」を作る
環境に左右されずに集中するためには、「特定の動作をすると集中モードに入る」というスイッチを作るのが有効です。例えば……
• 試験直前に決まった深呼吸をする
• 特定の香り(ミントや柑橘系)を嗅ぐ
• 試験開始前にノートに1行だけ書く習慣をつける
こうしたルーティンを作ることで、どんな環境でも「勉強モード」に切り替えやすくなります。
3. まとめ
タイピング音のような外部のストレス要因は、受験生にとって避けられないものですが、対策次第で気にならなくすることが可能です。
✅ まずは自分の反応を冷静に分析する
✅ イヤホンやホワイトノイズを活用する
✅ 座席変更が可能なら試す
✅ どうしても気になるなら、相手に丁寧にお願いする
また、受験生は不可抗力のストレスを受けることが多いため、以下のような対策を併用するのが効果的です。
✔️ 雑音耐性をつけるトレーニングをする
✔️ 「完璧な環境はない」と割り切る
✔️ 自分なりの集中スイッチを作る
受験勉強において最も重要なのは、どんな環境でも冷静に自分のベストを尽くせるようにすることです。ぜひ、日頃から実践して、試験本番でも動じない精神力を養いましょう!